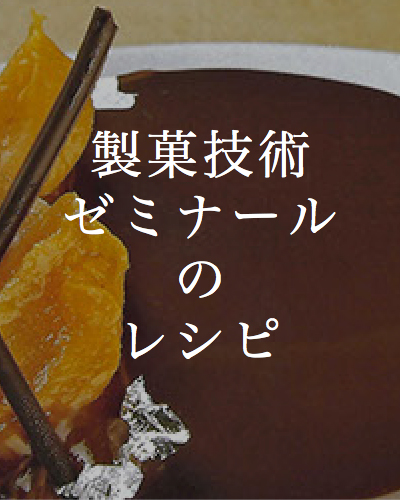講習会の情報
Workshop Information
2019-10-01
日本菓子教育センター 第18回研修会 ~「甘い物は太る」の誤解を解く~
日本菓子教育センター(髙井和明理事長/東京都新宿区)は、7月29日(月)、30日(火)の2日間に亘り、東京・浜松町の浜松町東京會舘で第18回研修会を開催、製菓学校の教職員や菓子団体の役員らが全国から参加した。
初日には、農学博士の橋本仁氏による『菓子と健康・甘味の機能~砂糖への誤解』のテーマでの基調講演と関連講演〔講師:全国和菓子協会専務理事 藪光生氏(同センター副理事長)〕を聴講した後、会場を移してグループ討論が行われた。
翌日はグループ討論の結果発表と意見交換が行われ、それを受けて藪副理事長が総評を述べた。
総評の中で藪副理事長は、「私達は昨日、砂糖を食べると太るというのは大きな誤りで、砂糖が糖尿病の原因ではないと学んだ。これを生徒達にしっかり理解させ、彼らが自信を持って菓子作りに取り組む事ができるように指導するのが皆さんの責務だろう。また、単に生きるためのエネルギーを考えれば、菓子は不要なものだと言える。しかしそれでも人々が菓子を食べたいと思うのは、それが癒しであり、心の満足に繋がるからだ。自分で作ったもので人を喜ばす事ができる。菓子作りの魅力はここに尽きるのではないか。皆さんはお客様に心の栄養を提供する生徒達を育てている。これを忘れてはいけないし、その事に自信と誇りを持って指導に当たって欲しい」と述べた。
この後、髙井理事長が、東日本大震災後に東北を訪問した際、(避難所でお菓子を配って涙を流すほど喜ばれたという)現地の組合員から「お菓子屋という職業を心から誇りに思う」と口々に言われ、菓子は、平時はもちろん、非常時に特にそういう役割を発揮すると如実に感じ、菓子屋の仕事の素晴らしさを実感したと語ると共に、「今回学んだ『“甘い物は太る”の誤解を解く』について、学園祭などで広くアピールして頂ければ、この勉強会が地域貢献にも繋がると思う」と挨拶して研修会を締め括った。
■基調講演「菓子と健康・甘味の機能~砂糖への誤解」骨子
糖質は、口や胃を経て小腸で「ブドウ糖」に分解されて血中に送られ、脳(知的活動)、筋肉(身体活動)、肝臓(化学反応)でのエネルギー源となる。
砂糖を摂取すると脳からインスリン(ホルモン)が分泌され、ブドウ糖を筋肉や脂肪の細胞に届ける事ができる。糖尿病は、糖質をエネルギーとして使うにために必要なこのインスリンの働きが悪く、血中の糖を細胞に取り込めない病気なので、血中に糖は多くても、実は糖欠乏病と言える。また、糖尿病の原因は、ストレスが最も多く、この他には体質の遺伝や運動不足、糖摂取不足、加齢などがあり、糖尿病患者は太った人よりむしろ痩せた人に多い。
砂糖のカロリーは、ご飯やパン等と同じ1g=4kcalだが、人は砂糖だけをご飯のように大量に食べる事はできない。「砂糖を食べると太る」や「砂糖を食べると糖尿病になる」は誤解である。同様に「砂糖を沢山食べると血液が酸性になる」や「砂糖は骨の中のカルシウムを溶かす」「砂糖をたくさん食べる子は、非行に走りやすい」なども誤解。
甘味は情緒と精神に安定をもたらし、心を安らかにする働きがある(快感中枢を刺激してエンドルフィンを分泌する)。また、アルコールの分解には果糖が役立つので、飲酒の後に甘いものを食べるのは有効。
脳の重さは体重の2%しかないが、24%ものエネルギーを消費するため、摂取カロリーのおよそ1/4が脳で消費される事になる。しかも脳のエネルギー源はブドウ糖のみで、さらに脳はこれを蓄える事が出来ない。そして、身体は内臓も筋肉も血液も絶えず作り替えられている。
■関連講演「栄養成分の働きとエネルギー代謝について」骨子
摂取した食物は、「エネルギー源」(基礎代謝、活動代謝など)と「身体の構成成分」(筋肉・内臓・血液など)に使われるが、糖質(炭水化物)は主としてエネルギー源にしかならず、タンパク質はエネルギー源にも身体の構成成分にもなる。
1日に2300kcalを摂取する一般的な成人男性の場合は「基礎代謝」に1530kcalが必要で、この他に「食事誘発生熱産生」(食物の消化・吸収・運搬のための熱量で、摂取カロリーの約10%)に230kcalが必要なため、残りの540kcalが活動のためのエネルギーとなる。同様に1750kcalを摂取する成人女性は、基礎代謝に1150kcal、食事誘発生熱産生に175kcalが必要で、活動代謝は425kcalとなる。
そこで炭水化物の摂取を抑えると、タンパク質が優先的にエネルギー源として使用される。そうすると構成成分が不足するので身体の組織が弱くなる。また、これを補うため身体は基礎代謝を下げる。基礎代謝が下がると体温が下がり、血液の循環が衰えて冷え性になり、低血圧あるいは高血圧になる等の不都合が生じる。そして常に飢餓状態の身体となり、結果的に太りやすい体質になる。
2019-09-10
クープ・デュ・モンド日本実行委員会
2019年代表選手による特別講習会を開催
クープ・デュ・モンド日本実行委員会(小澤俊文実行委員長)は、6月18日(火)・19日(水)の2日間、ドーバー洋酒貿易(株)を会場に、表題の講習会を実施した。
国際製菓コンクールとして名高い「クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー」は、1989年にフランス・リヨンにて初開催され、今年2019年大会で30周年を迎えた。日本からは、五十嵐宏氏(パティスリー ラ・ローズ・ジャポネ)を団長に、リーダーでアシエット・デセール/ピエス・ショコラ担当の西山未来氏(㈱シュゼット・ホールディングス)、アントルメ・ショコラ/アメ細工担当の伊藤文明氏(パティスリーメゾンドゥース)、アントルメ・グラッセ/氷彫刻担当の小熊亮平氏(㈱グルメ和光)が出場し、見事銀メダルを獲得した。
講習は、午前中に各選手がそれぞれ担当した味覚作品の製法を解説し、午後からは、西山・伊藤氏による各ピエス作品ならびに小熊氏による氷彫刻の実演が同時進行で行われた。助手として2021年度大会に出場する、原田誠也氏、塚田悠也氏、赤羽目健悟氏の3選手がサポートについた。
この間選手や団長の五十嵐宏氏は、大会までの道のりや大会中に起こったアクシデント、またレシピやフォルムが決定するまでの紆余曲折などのエピソードや苦労話をコメントした。
会場には、クープ・デュ・モンド出場を目指しているパティシエを中心に、オーナーシェフの姿も散見されるなど各日100名超の受講者が集まった。
同実行委員会では、9月18日(水)に2021年大会に出場する3選手による国内予選出場を目指すパティシエを対象にした講習会を実施予定。
2019-09-10
クラブ・ドゥ・ラ・ガレット・デ・ロワ
2019年伝統菓子勉強会を開催
クラブ・ドゥ・ラ・ガレット・デ・ロワ(西野之朗会長)は、6月26日(水)にドーバー洋酒貿易(株)講習会場にて、「Nouvelle tradition à ma façon ~新たな伝承、私流のお菓子~」をテーマに勉強会を行った。これは毎年開催しているもので、フランス伝統菓子の本来の魅力や文化を大切にし、伝えていく目的で行っている。
今年の東京会場では、大亀善孝氏(ヴィロン)と島田徹氏(パティシエ・シマ)の2名のシェフがデモンストレーションを担当した。
講習会場には、同クラブ会長の西野之朗氏をはじめとした理事やシェフ会員、クラブ会員が集い、実演終了後はシェフメンバーが持ち寄った菓子にまつわるエピソードに耳を傾けながら、15種類以上の菓子を試食した。
また、同様の勉強会が大阪会場にて6月20日(木)に行われた。
勉強会(東京会場)参加シェフリスト
| 店名 | 名前 | 菓子名 |
|---|---|---|
| メゾン ドゥース | 伊藤 文明 | ガレット・デ・ロワ ヌーベル |
| アヴランシュゲネー | 上霜 考二 | キャレ パッション |
| ヴィロン | 大亀 善孝 | ベラベッカ |
| パリセヴェイユ | 金子 美明 | タルト リュバーブ オランジュ |
| オクトーブル | 神田 智興 | パリブレスト |
| パティスリーユウササゲ | 捧 雄介 | スリジエ |
| パティシエ・シマ | 島田 徹 | タルトシトロン エマ |
| リョウラ | 菅又 亮輔 | ケークオフリュイ |
| ジャンポール・チェボー | ジャンポール・チェボー | マカロン・ド・ナンシー |
| キャロリーヌ | 中川 二郎 | ドミノ |
| メゾン・ド・プティフール | 西野 之朗 | Enfer des Anges |
| 菓子工房グリューネベルク | 濱田 舟志 | ガレット・デ・ロワ カラメルブールサレ |
| ル・ポミエ | フレデリック・マドレーヌ | モワルーショコラ アマレーナ |
| フランス菓子 トワグリュ | 三鶴 康友 | ビスキュイ・ド・サヴォワ |
| ダロワイヨジャポン | 持永 定治 | オペラ フォレノワール |
| ドゥヴルベボレロ | 渡邊 雄二 | ノネット |
| ノリエット | 永井 紀之 | ボンブグラッセ |
| メゾン ジブレー | 江森 宏之 | コクトーレン |
2019-09-10
技術コンクール(2020シャルル・プルースト杯選考会)に向けての技術講習会
~2018シャルル・プルースト杯総合優勝 石黒啓太氏によるコンクールテクニック~
内海会(横田秀夫会長)は、6月12日(水)日本製粉(株)東部技術センターにて表題の講習会を開催した。講師は、2017年の内海杯で 優勝して日本代表権を得、翌年パリで開催された国際コンクール「シャルル・プルースト杯」で総合優勝した石黒啓太氏(イーストギャラリー/(株)シュッティヤナセ)。解説は、内海会理事で2008年のシャルル・プルースト杯で総合優勝した冨田大介氏(カルチェ・ラタン)が担当した。
講習会では、マロンをテーマにした生菓子を講習した後、メインのチョコレートに、アメとパステヤージュを組み合わせたピエスモンテの製法について「実際にパーツを見て触れられるのは講習会に来た人の特権です」(冨田シェフ)の言葉通り、型の作り方や、型やパーツを強固に貼り合わせるための雄雌(凸凹)の作り方、壊れにくい重心の採り方、着色やツヤ出しの方法などを説明し、製作のポイントはもちろん、壊さず搬入するために、ルートの下見を行うなど細心の注意を払った経緯等も語られ好評を博した。
2019-09-10
日仏商事 フレキシパン新商品を使用した講習会を開催
グラスファイバー不使用で複雑な形も表現できる“フレキシパンインスピレーション”新登場
当工業会賛助会員の日仏商事株式会社(筒井潤代表取締役社長/兵庫県神戸市)は、6月28日(金)同社東京事業所にて、9月からリブランディングするフレキシパン(ドゥマール社)の活用をテーマに講習会を開催した。
講習会では、シャンパーニュ地方にあるブーランジュリーの4代目、ギョーム・ショッポヴェン氏を講師に迎え、パティスリー、ブーランジュリー向けの焼き菓子やヴィエノワズリーのデモンストレーションが精力的に披露され好評を博した。
■新しくなったフレキシパン(3タイプ)
フレキシパンオリジン:グラスファイバーが入り、丈夫でフレキシブル
フレキシパンエアー:タルトや焼き菓子、シュー生地、パンに最適なメッシュタイプ
フレキシパンインスピレーション:グラスファイバー不使用で、複雑な形が表現でき、特注品も対応可