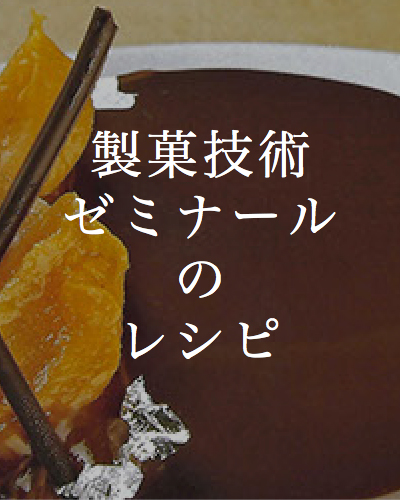講習会の情報
Workshop Information
2019-12-06
クープ・デュ・モンド日本実行委員会
2021年日本代表選手による特別講習会を開催
クープ・デュ・モンド日本実行委員会(小澤俊文実行委員会)は、9月18日(水)にドーバー洋酒貿易(株)講習会場にて、今年3月に行われた国内予選で選出された日本代表選手による講習会を実施した。本選出場を前に現役代表選手が講習会を実施するのは初の試みで、次の日本代表を目指すパティシエを対象に行われた。
講師を務めたのは、チームリーダーでアメ細工ピエスモンテとアントルメ・ショコラ担当の塚田悠也氏(東海調理製菓専門学校)、チョコレート細工ピエスモンテとアシエット・デセール担当の原田誠也氏(クラブハリエ)、氷彫刻とアントルメ・グラッセ担当の赤羽目健悟氏(帝国ホテル東京)。解説は歴代の代表選手が担当し、団長を務める五十嵐宏氏(パティスリー ラ・ローズジャポネ)、2019年代表の西山未来氏(シュゼットホールディングス)、同・伊藤文明氏(メゾンドゥース)、同・小熊亮平氏(グルメ和光)、2011年・2015年に出場した中山和大氏(オクシタニアル)が、本選・国内予選や審査員としての経験を踏まえたアドバイスを行った。
講習の前半は、講師が国内予選時の味覚作品について製法のポイントを口頭説明し、それぞれ試食も供された。続いて、アメ細工ピエスモンテを塚田氏が、チョコレート細工ピエスモンテを原田氏がモンタージュしながら、特別な技法や注力した部分について解説した。赤羽目氏による氷彫刻の実演では、より多くのパティシエが始められるように、最低限必要な道具やその入手方法などを具体的に説明した。受講者は、終始積極的に質問を行い、講習終了後も熱心にアドバイスを受けていた。
同実行委員会では、今後も講習会やワークショップ等を企画し、より多くのパティシエが、製菓における代表的な国際コンクールであるクープ・デュ・モンドを目指せるようサポートしていくとしている。
※国内予選の模様は2019年6月号(VOL.595)に掲載しています
2019-12-06
カルピジャーニ・ジャパン 第1回ガストロノミー・ジェラート講習会
~カクテル・前菜・メイン・デザートとジェラートの融合~
当工業会賛助会員のカルピジャーニ・ジャパン株式会社(ロレンツォ・スクリミッツィ代表取締役社長/東京都世田谷区)は、9月26日(木)同社セミナールームで、レストランシェフの入門セミナーとして、初の「ガストロノミー・ジェラート講習会」を開催した。
講習会では、「ガストロノミー・ジェラートの概要」、「原材料と構成」、「ホワイトベースからのバリエーション」、「ガストロノミー・ジェラートのコスト例」、「ガストロノミー・ジェラートのメニュー例」、「業態別のマシン提案」について、カルピジャーニ・ジェラートユニバーシティのジャンパオロ・ヴァッリ氏と茂垣綾介氏(カルピジャーニ・ジェラートユニバーシティ/ジェラテリア アクオリーナ)による講義とデモンストレーションが行われ、アンチョビやゴルゴンゾーラのジェラートを使ったメニューの試食が振る舞われた。
終了後には、スクリミッツィ社長、ヴァッリ氏、茂垣氏の各氏が「ガストロノミー・ジェラートは、ヨーロッパの星付きレストランが注力しており、日本でも大きな可能性を秘めています。製造には、乳製品の風味を抑え素材の風味を強める配合バランスが必要ですが、弊社はマシンの専門メーカーとして皆様をサポートいたします」(スクリミッツィ社長)、「日本での活動に関われて嬉しい。控えめな甘さを好む日本人には、塩味のガストロノミー・ジェラートが受けると確信しています」(ヴァッリ氏)、「食事に使われるすべての食材を使って作られるガストロノミー・ジェラートは、アペリティフ、前菜、メイン、食後のデザートのどのシーンにも合い、身近な食材で作れるので、是非手掛けて欲しい」(茂垣氏)とそれぞれスピーチした。
■問合せ:カルピジャーニ・ジャパン(株) TEL.03-5779-8850 FAX.03-5779-8853
e-mail:sportello@carpigianijapan.co.jp
2019-12-06
エコール ヴァローナ
MOFヤン・ブリス氏による特別講習会を実施
当工業会賛助会員のヴァローナ ジャポン株式会社(東京都千代田区/ブルーノ・ボードリ代表取締役社長)は、エコール・ヴァローナ東京にて、9月2日(月)~3日(火)の2日間に亘り表題の講習会を実施した。
ヤン・ブリス氏は「フォション」、「コンコルド・ラファイエット」、「ホテル・ブリストル」、「ダロワイヨ」など数々の高級ホテル、老舗菓子店で修業を積み、ダロワイヨ在職中の2011年にMOFを受章した。また、製菓技法に新たな歴史を刻んだデコレーション「Tourbillon(トゥールビヨン)」で一世を風靡し、その名を世界に知らしめた。現在は、フランスパリ郊外のソ=レ=シャルトルーの自店「トゥールビヨン」を経営し、コンサルタントとしてもグローバルに活躍中。
今回の講習会では、アントルメ、タルト、プティガトー約8品の実習形式での研修会を実施した。MOF本人自らが指導するというまたとない機会に、8名が受講し充実した講習会となった。
2019-12-06
合同酒精 オクシタニアル 中山和大氏による製菓技術講習会
~国際コンクール代表シェフの味と技~
当工業会賛助会員の合同酒精株式会社(西永裕司代表取締役社長/千葉県松戸市)は、9月25日(水)東京・秋葉原の正栄食品工業株式会社にて表題の講習会を開催した(後援:内海会)。
講師を務めた中山和大氏(アクシタニアル)は、「リモージュ」「六本木ヒルズクラブ」「マンダリンオリエンタル東京」を経て、2014年に『オクシタニアル』(東京・水天宮)のシェフ・パティシエに就任。クープ・デュ・モンド準優勝(2015年大会)などの受賞歴がある。
講習会では「ネプチューン」シリーズを中心とした合同酒精の洋酒を使用した5製品について、どこから食べても、狙った味が伝わるような構成を心掛ける。バターを使った生地は冷蔵すると硬くなるので、オペレーションを考えて米油(クセが無く健康志向にもマッチ)を使用する。手間が省けて味に遜色が無ければ、レモンゼストの代わりにレモン・ペーストを使うなど市販品を活用する。イタリアンメレンゲの(卵白の加熱による)食感や風味が苦手なため、冷凍卵白と水飴(ハローデックス)でメレンゲを作り、ムースに合わせるクリームの一部に置き換えている。ナパージュを自家製にしているのは市販品より美味しくコストも低いから・・・等々、シェフ・パティシエとして、美味しさと効率を追求した仕事の方法などを説明しながらデモンストレーションを行い、アメ細工の基本技術も披露して好評を博した。
2019-10-01
内海会
技術講習会 内海会味覚コンクールに向けて ~アントルメ・プラリネ~を開催
内海会(横田秀夫会長)では、7月10日(水)に、ドーバー洋酒貿易(株)講習会場にて、今年の11月11日に開催される「内海会味覚コンクール」に向けて、表題の講習会を実施した。
講師は内海会理事4人のシェフが務め、アーモンドやヘーゼルナッツ等様々なプラリネを主体にした味の構成についての考え方を披露した。
はじめに寺井則彦筆頭理事(エーグルドゥース)が、プラリネの定義を解説。続いて、野島茂氏(グランドハイアット福岡)が、プラリネとバタークリームを組み合わせたアントルメを紹介。同割のヘーゼルナッツとアーモンドを使用した自家製プラリネは、しっかりローストして味をしっかり出したとして、「多くの作品を試食する審査員からすると、何を食べさせたいのか明確な作品が印象に残る」とコメントした。
午後からは、安里哲也理事(ザ・キャピトルホテル東急)が、プラリネとババロワーズを組み合わせ、さらにアプリコットをアクセントとしたアントルメを、続いて和泉光一理事(アステリスク)が、プラリネとメレンゲを組み合わせたアントルメを紹介した。和泉氏は、「今回与えられたテーマは、チョコレート不使用なのでハードルが高いと思うが、新しいアプローチでレシピ開発ができ、それは自分の肥やしになる」とコメントした。
講習終了後には、味覚コンクールの考え方、そして傾向と対策について安里理事が説明し、審査基準について「複雑になりすぎない事、食べやすいサイズである事、ナッツならびにキャラメリゼした風味そして合わせる素材の味がしっかり出ている事」と説明がなされた。寺井筆頭理事は、「今回は、プラリネの味をマスキングしてしまうチョコレートを使用しないというテーマを設けた。プラリネがファーストフレーバーで、アクセントとしてアントルメを支える素材がセカンドフレーバーに、そしてインパクトを与えるサードフレーバーというように、3つ位の味のコンポジションが良いのでは」とコメントした。
5回目となる内海会味覚コンクールのテーマは、「チョコレートを使わずに、アーモンド、ヘーゼルナッツなどいろいろなプラリネを主体に味を表現する」。グランドプリンスホテル高輪を会場に11月11日に実施する。申し込み締め切りは10月28日(月)で先着40作品の募集となっている。